井戸と花束
♪井戸の底には寂しいこどもがいて
空から贈られた花束を受け取ったんだ
そんなところにこどもがいるなんて
ほんとは誰も知らなかったけれど
こどもはそれが自分に贈られたものだと信じたんだ
花束を抱きしめて泣いて泣いて
嬉しくていっぱい泣いたんだ
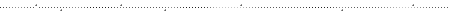
古都イスファリーの路地裏には、およそ数千の露店がひしめいている。
占星術師が祝福を込めた色鮮やかなステンドグラス・ランプ、宮廷魔術師御用達の四大元素各種原石をびっしりと並べた魔鉱石店、ドラゴンの肝臓を専門に商う薬問屋や、南国の猿の尾を軒先に束ねてぶらさげた衣料品店――とにかくヒトの生活に必要なものなら、なんでも揃う。
「ねえ、琥珀グラスの香水瓶はないの?」
「さあさあ魔法の杖の大バーゲンだよ! いらっしゃい! アルサム(見てってよ)!」
「今日は肉が高いねェ……」
古都を訪れた観光客も地元民に混じって、土産物を探す。夜が明けるまで、どこもかしこも賑やかだ。軽く五カ国語分の挨拶が飛び交い、目抜き通りでは怒鳴るように話さなければ、会話だって成り立たない。
「さ、安くするよ兄さん! シナモンが一束で……あ、グリム人か? レイ・バ、ラスタ・シナモス・ラカ・リスタ(超安いよ、シナモンが一束でたったの)……」
昼時に差し掛かり、食事を求める人々で路地はさらにごったがえしていた。山羊の肉汁が弾ける音、バターとニンニクが焼ける香ばしい匂いが、ふわりと漂ってくる。暗い路地の横道に佇んでいたラウムは、渋い顔で腹を押さえた。昨日の昼から何も食べていないのに、こんなとこにいたら空腹で倒れてしまう。少し休んだら、また移動しよう。
美味しそうな匂いを振り払うために、ラウムは、抱いていた大きな花束に顔を埋めた。彼女の真っ赤な長い三つ編みが、花束に色を差す。幼い顔を花の合間に埋めたまま、ラウムは溜息をついた。
「花なんか売ったことないのにさぁ……」
細い腕にたっぷりと抱えた花束は、朝から一輪も売れていなかった。真っ赤な百合も、白と山吹の勿忘草も、鮮やかな橙の薔薇も、水気を失って萎れかけている。これじゃあ、売れるものも売れないだろう。
「そもそも、誰が私なんかから買うんだよ」
しかし、売りきるまで帰ってくるな、と朝一番で店から放り出されたのだ。売り上げ金を持って帰らなければ、雇われて一日目で首になってしまう。それは避けたかった。やっと、久しぶりに仕事にありつけたのに。
(どうしようもなかったら、売り上げ分の金だけでも……)
空腹で霞む頭でぼんやり考えていると、ばしゃん、と裸足の足首にぬるい水が掛かった。
ラウムが振り返ると、店のおばさんが、バケツの水を捨てた体勢のままで固まっていた。しまった、と慌てるような顔が、ラウムの真っ赤な髪と目の色を見るや一変し、蔑むような眼差しになった。
「うちの前に立たないでちょうだい、赤髪(ラジャン)」
ご丁寧に追い払う手振りつきだ。ラウムは大人しく従った。
これでも、子供相手だから、手加減されている方なのだ。この古都では、いや、この国では、赤い髪の人間は、どこにいっても居場所がない。
路地の人混みに紛れて歩いていると、人の流れを二つ感じる。一つは、地元民の流れ。ラウムの赤い髪を見て、あからさまに離れてゆくもの。もう一つは観光客の流れだ。物珍しげに近づいてきて、花束と彼女の髪を眺め、ひっそりと離れてゆく。ラウムは人通りが激しい、観光客がひしめくメインストリートへと向かうことにした。
(狙うなら、馬鹿で金持ちな観光客。浮かれてる男性。財布の紐が緩そうな奴……)
「寄るな、泥棒(ラッジャ)」
擦れ違いざまに誰かに罵られたが、ラウムは息をするように無視した。構っていたらきりがないし、実際、彼女は昨日までスリで食べていた。
ひしめく店と、流れる人波のよどむ場所。早足で歩きながら、ラウムは慣れた眼差しで人混みを見渡した。狙い目の人間は、スリの時と大して変わらないはず。
観光客を何十人と見送って、ふと、ラウムは一人の男に目を止めた。お供らしき人間を二人連れた、小太りの若い男がキョロキョロふらふらと歩いている。仕立ての良い服、外套から覗く時計の金鎖。あれ、今に絶対スられるな、とラウムは思った。こんな場所で富を隠そうともしない人間。間違いなくカモだ。普段の癖で、人混みに紛れながらそっと擦れ違おうとして、ラウムは慌てて止めた。大きな花束を抱えているから、財布に手を伸ばすことはできない。もし日が暮れるまで一輪も売れなかったら、売り上げ分はスリか何かで補うしかないだろうが、とりあえず、今はまだやめておこう。
人の流れが激しすぎて、立ち止まるのは難しい。ラウムは、彼がメインストリートを出るまでそっと後をつけた。寂れた横道や道端のゴミ、埃に煤けた店が目立ち始めても、男は足を止めない。逆に物珍しいのか、どんどん先に進んでゆく。
さてどうしよう。少し心細くなってきた頃に、安心させるような笑顔で、さも幸福を分け与えるような感じで出てみたらどうだろうか。同情を誘うよりは、そっちの方が効きそうな気がする。
じっと売りつけるタイミングを伺っていたラウムは、ふと、視線を感じて辺りを見回した。そして一本隣の横道の少年と目が合った。
(……あ)
自分と同じように薄汚れた裸足の少年だった。ラウムは、彼もまた、あの男を狙っているのだ、とすぐ分かった。髪は黒かったが、痩せこけた細い手足が、彼の空腹を教えていた。あの子は男の財布をスるだろう、隙さえ見つかればすぐにでも。まずい、と思った。その前に売りつけなければ帰れない。
ラウムはパッと走り出した。
「旦那さん! 旦那さん、ねえ、待って!」
男たちが振り返る。ラウムは、長い距離を走ってきたかのようにわざと息を切らせて、安堵したような笑顔を浮かべてみせた。そして、ぐいっと花束を突き出した。
「あのっ! お花、買いませんか?」
しまった、と思った時にはもう遅い。唐突すぎだ。慌てて売り口上を並べようとしたが、今まで一度も言ったことがない言葉が急に言えるはずもなかった。男たちは、じろじろとラウムを眺めただけで、また歩きだしてしまった。
「あっ……。……。ま、待って! お願い! 買ってもらわなきゃ帰れないの!」
もうやけくそだ。馬鹿で可哀想な子供の役を演じよう。ラウムはしつこく男たちの後を追いかけ、懇願しつづけた。
「いらないって言ってるじゃないか、君。困るよ」
「そんなこと言わずに……ほら、すごい良い色でしょ? 旦那さん、良い男だから、誰かにあげるのにぴったりだよ! ねっ? 買ってよ、旦那さん!」
「そんなこと言ってもなあ……」
「お願い! ねえ、お願い! 旦那さん、お金もちなんでしょう? 全部でたったの五百クルシュだから!」
ちなみに、地元相場は二百だ。観光客価格しか知らない男は、それでも安いと思ったらしい。微妙に表情が変わった。
「全部? 全部はさすがにいらないな。一輪ならいくらだ?」
「ええっ、一輪? 一輪だけ買ってどうするの? 全部買おうよ旦那さん! 女の子にプレゼントしたら、大喜びするよ!」
ラウムは畳みかけた。一輪売れたって何の足しにもならない。五百で安いと思えるのなら、全部買えば良いんだ。ラウムは小走りになって付きまとい、大声をあげた。
「買ってよ、旦那さん!」
男のお供が、じろりとラウムを見た。彼女の赤い髪、何の起伏もないがりがりの身体、薄汚れた裸足の足。どうしますか、と伺うように男を見る。男は何かを言おうとして、やめて、なげやりに片手を振った。
「ああ、もう、めんどうだ。買えば良いんだろう。いくらだ?」
「五百だよ! ありがとうっ、旦那さん!」
ラウムはぱっと笑顔を浮かべた。飾り気なしの本気の笑顔だった。値切りもしないなんて、なんて良いお客なんだ。これで帰れるし、ご飯も食べれる。放られた銀貨をしっかり握りしめ、ラウムは心からの感謝を込めて、花束を差し出した。
「旦那さんに、旅の祝福がありますように!」
「ああ、どうもね」
男は苦笑いを浮かべて花束を受け取ると、さあもう用事は済んだだろう、早くどっかへ行ってくれないか、とでも言いたげに首を傾げた。ラウムはぺこりと頭を下げて、さっと踵を返し、走りだした。
正直、あの男の大きな財布をスッてしまった方が、稼ぎにはなったのだ。でも、物の対価としてちゃんと正しいお金を貰うのは、久しぶりで、なんだか気分が良かった。さあご飯を食べよう。路地裏の小屋で待っている、小さな弟たちの分も買って帰ろう。
路地へ出る前に、ラウムはもう一度お礼が言いたくなって、振り返った。すると、男があの花束を枯れ井戸に投げ込んでいるところだった。
(あっ)
水音さえ無かった。一瞥もくれずに、片手で放っただけで、男はあの花束を井戸に捨てたのだと分かって、ラウムは立ち尽くした。男たちが何か喋りながら路地の奥へ消えていく。今、自分の中に生まれている感情が何なのか、ラウムには全く分からなかった。ただ、右手で握りしめている銀貨が、どんどん生ぬるく気持ち悪いものになっていくことだけが、分かっていた。
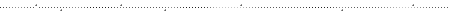
「ちなみにばあちゃんが、あれは悔しさから来る怒りだったんだって気づいたのは、私の母ちゃんを産んだ後になってからさ」
「ふーん、へえー。知りもしない故人について随分詳しくなりましたよ。それで?」
「それでって?」
「井戸の中を確かめに行ったりとか、その男ども走って殴りに行ったりとか、なかったんです?」
「いやあ、ないない。そんなドラマチックな話じゃあないよ」
そうですか、と適当に相槌を打って、旅人は額の汗を拭った。木陰にいても汗が吹き出る。旅人はベンチの金属部分に腕を這わせて、少しでも涼を取ろうとした。あまり変わらなかった。
「でも、あの枯れ井戸に水が戻ったのは、男が花束を投げ入れた次の日からなんでしょう?」
だらしない体勢のまま、旅人は顎をしゃくった。真っ白な石畳で舗装された、塵一つ落ちていない小道の向かい側、三十歩ほど離れたところに、美しく装飾された井戸がある。その周囲には観光客が群がっていた。現地の観光ガイドがそれらしく語る井戸の物語が、旅人の座るベンチからでもよく聞こえる。いわく、精霊がどうの、領主がどうの、花束に込められた魔力がどうのこうの……。
「ああ、次の日から水が戻ったのは本当さ。ガイドが喋るのはほとんど嘘八百だけど、そこのとこだけは本当だよ」
旅人の隣のベンチに腰掛けていた老婦人は、にっこりと笑った。ほとんど白くなった髪に、まだ幾筋かの赤が残っている。
「昔は、あの辺一帯には生きてる井戸がなくてねえ、そりゃあ近所中で大騒ぎになったそうさ」
「それはそれは。その男も良い仕事をしたもんだ」
適当なことを言って、旅人はけらけらと笑った。およそ百年前の春、喧噪とゴミにまみれていたらしい路地裏が、今はこんなにも整備された広く美しい散歩道になっているなんて、おかしかった。
「井戸だけ残して、家はみんな壊しちゃったんです?」
「焼けちまったんだよ。百年で色んなことがあったからねえ、この街も。名前が変わって、国境が変わって、人の考えも変わったよ。本当のことなんか忘れられるだけさ」
かんからからん、ちりんからん、と金属壷に結わえた鈴を十もいっぺんに鳴らしながら、水売りが通りをやってきた。
「井戸水だよォ。古都ランファラードいち有名な、いわくつきの井戸水、氷の魔法石でしっかり冷やして、一杯たったの三十カルセだよォ」
気だるそうな呼び込みだったが、そのへんをブラブラしていた観光客たちが、わっと水売りのもとへ群がっていく。みんな、夏の正午に参っていたのだろう。
「兄さんも飲んできたらどうだい。甘くて良い水だよ」
「へえ、どうだか。観光客向け値段の、観光客向け水道水だったりしないんですか?」
「あのじいさんが売ってるのは本物さ。ほんとほんと。行っといでよ」
「そうですか。じゃ、いただいていきましょうか。今日は流石に暑すぎる」
よっこらしょ、と声に出しながら立ち上がり、旅人は背筋を伸ばした。木陰を出ると夏の日差しが眩しい。水売りが背負う金属壷がキラキラと太陽を反射している。彼は壷を背負ったまま、手元の木製レバーをガシャンと操作して、観光客一人一人に水を注いで回るのだ。使い捨ての素焼きカップで思い思いに井戸水を楽しむ彼らのそばで、ふいにアコーディオンが歌い始めた。街の歌い手だ。
「井戸の底には寂しいこどもがいて
空から贈られた花束を受け取ったんだ
そんなところにこどもがいるなんて
誰も知らなかったけれど
こどもはそれが自分に贈られたものだと信じたんだ
花束を抱きしめて泣いて泣いて嬉しくていっぱい泣いたんだ
だから井戸に水が戻ったんだ」……
薄汚れた格好で歩きながら、歌い手たちは街の伝説を(観光客向けに)美しくアレンジする。井戸水を飲む何人かがフラフラと歌声のそばに寄ってゆき、楽器ケースにコインを投げ入れていた。
旅人は最後に振り返って、聞いてみた。
「おばあさんはどう思います? ああいうの」
「良いんじゃないかい。好きに稼げば良いのさ」
「いやそうじゃなくて……まあいいや」
「ちなみに、子供バージョンじゃなくて精霊の恋バージョンもあるぞ」
「はあ」
「失恋のショックのあまり枯れ井戸の底で死んでいた水の精霊は、額の上に振ってきた花束の口づけで目を覚まし、自分は恋人に見捨てられた訳じゃなかったんだって涙を流したってさ」
「大変ですね、井戸も」
「そうさねえ。良いじゃないか、ロマンチックで。本当はたまたま捨てられただけの花束だったとしてもね」
「じゃ、降ってきたのは花束じゃなくてほんとはゴミだったなんて知ったら、子供にせよ精霊にせよ、ショックでまた死にそうですね。みんなで真実を隠さなくちゃ」
「そんなこと、井戸はもう知ってるだろうよ。でもま、大丈夫だ。今はちゃんと、ああやって愛されてるからな」
旅人はしばらく考えてから、「なるほど」と呟いた。確かにそのとおりだ。彼は笑って、ぺこりと頭を下げた。
「じゃあ、おばあさん。良い話をどうも」
「こちらこそね。年寄りの独り言につきあってくれてありがとうよ」
「いえいえ。楽しかったですよ」
旅人と老婦人は、ひらひらと手を振り合った。互いの名前も知らないし、もう会うこともないだろうが。
「良い旅があるように、旅人さん」
「あなたに旅の祝福を、おばあさん。それでは」
旅人は帽子を被りなおすと、白く美しい石畳をぶらぶらと歩いていった。観光客に混ざって、井戸のそばにそっと佇んでみる。綺麗に手入れされた井戸には蔓草が這い、木戸の透かしの奥には微かに水音が轟いていた。
「お兄さんもどう? たったの三十カルセさァ」
いつのまにか、隣に水売りが佇んでいた。旅人はちょっと笑って、頷いた。
「じゃ、いただきます」
「どうもね」
ガシャン、とレバーが鳴る。温度差のためだろう、表面にびっしりと水滴をまとった金属壷は、氷の魔鉱石を効率的に動かすために、楽器のような複雑な形を成している。美しいなぁ、と旅人は思った。
水を湛えたカップを旅人に渡すと、水売りはさっさと別の客のところへ行ってしまった。旅人はしばらく辺りを見回してから、こっそりと、井戸に向けて杯を掲げた。
「乾杯、精霊さん」
FIN
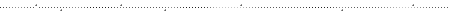
文藝部誌「游」タイムカプセル記念誌掲載・一部修正
五年越し「井の底の歌声」にあてた一種のアンサーソング
←Back
|